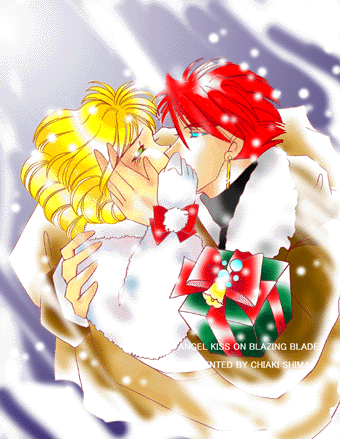|
白い息を弾ませながら、アンジェリークは走る。
本当はもっと早く待ち合わせ場所について、時間ぴったりに来る彼を待っているはずだったのに、急な事情とはいつも狙いすましたようにこんな大事なときに起こるものだ。
先ほどから降り始めた雪が足下を滑らせそうになる。駆け寄る先には、赤毛の長身の男性。どれだけ遠くからでもアンジェリークには彼の姿が見える。
「……ごめんなさい、オスカーさま……。遅くなっちゃった……。」
オスカーは白い雪をうっすらと赤い髪にかけたまま、黙ってアンジェリークを見つめる。
「怒っていらっしゃるの……?」
おずおずとオスカーを見上げる。オスカーははめていた手袋を外すと、アンジェリークの頬に手を寄せる。アンジェリークはきゅっ、と身をすくませるが、その大きな手がアンジェリークの頬を包み込んでいるのに気づいてそっと目を開ける。
「こんなに冷たくなって……。」
冷たい風を受けて、アンジェリークの頬は痛いくらい冷え切っている。 心配そうにのぞき込む氷青の瞳はその色とは裏腹に射るように熱い。アンジェリークの頬が赤いのは冷たい風のせいだけではない。跳ね返りそうな心臓の音を聞かれそうでアンジェリークは慌てて真っ赤な顔をそらそうとする。
「わ……私は全然……。走ってきたから、そんな、熱いくらいで……。それより、オスカーさまこそこんな寒い中ずっと……。」
目が……そらせない……。 心臓の音も、真っ赤になった顔も隠せそうもなく、アンジェリークは言葉を続けることができない。心が……熱い……。
「そうだな……。ちょっと冷えたかも知れないな……。」
オスカーは片方の腕をアンジェリークの背にまわし、ぐいっと抱き寄せる。すっぽりとアンジェリークの小さな体をコートの中に包み込むと耳元でささやく。
「暖めてくれるかい……?天使さま……。」
冷え切った頬を包む大きな手は温かく、そのままアンジェリークのピンク色の唇をゆっくりと導く。アンジェリークは大きく開かれた目をそっと閉じる。
一瞬の永遠
このまま、何もかもが止まってしまうような、そんな不思議な感覚。彼のキスはいつも包み込まれるように長く、熱い。彼も自分と同じように冷え切った体が熱く感じられているのだろうか。そうあって欲しいとアンジェリークは重ねた唇を自分からもう少しおしあててみる。アンジェリークの少し開いた唇にそっと舌が入ってきて、歯列を探り、舌に絡まる。
「……ん……。」
足下から伝わってくる寒さも、冷たい風も感じない。感じられるのはただ彼の唇と熱い甘やかな痺れ。
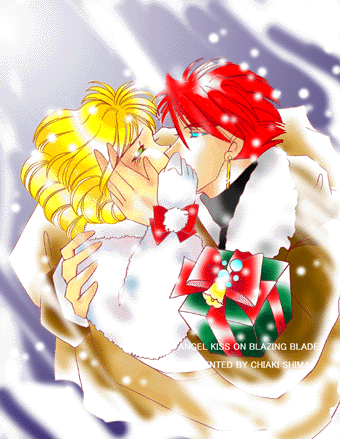
「プレゼント……、落ちちゃてたんだ……。」
長い口づけのあと、ふと気がつくと、アンジェリークの足下には小さな包みが落ちていて、半分雪に埋もれている。
今日は12月21日。誕生日プレゼントなのに何だかラッピングがクリスマスっぽくなってしまった。本当はキリストは3月に生まれたんだと教えてくれたのは、誰だったろう。でも、長い間苦難に虐げられていた人々は救世主のイメージを長く暗い夜を照らす聖なる者の降臨としてとらえ、以来クリスマスは冬、それももっとも夜の長い日となったのだ。
「……あなたは私の聖なる人だもの……。」
アンジェリークは誰にも聞こえないような小さな声でつぶやくと、プレゼントを拾い上げオスカーを見上げる。一年で一番長い夜を照らす聖なる者。こんなにこの方にふさわしい誕生日ってあるだろうか。
「お誕生日、おめでとうございます。」
ちょっと照れたような、でも幸せそうな笑顔でアンジェリークはプレゼントを渡す。
「でも、俺にとっては君とこうしていることが最高のプレゼントなんだがな。」
プレゼントを受け取りながら、オスカーは続ける。
「今夜は一番夜が長い日なんだぜ。こんな日に誕生日って言うのも悪くないな。」
いたずらっぽく、ちょっと意味ありげに笑いかけるオスカーにアンジェリークは恥ずかしそうに顔を赤らめて、でもそっと身を寄せた。 雪は静かに降り、身を寄せ合う恋人たちのために夜を照らす。
Many Happy Returns of The Day.
Angel Kiss on Blazing Blade.
|